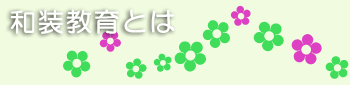
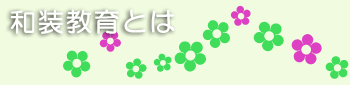

戦後、生活の洋風化に伴い、日常生活の中で着物を着る機会は少なくなりました。一方、公式行事や社交の場では、和装が大きな役割を果たしています。日本が国際化していくうえで、今後さらにその重要性は高まるものと思われます。
また最近では、浴衣(ゆかた)が夏の装いとして若者の人気を集めています。日本独自の文化と生活様式のよさが、若い人にも受け入れられ、生活のスタイルや意識の根底に受け継がれているからでしょう。
このように世界に誇れる日本の民族衣装・着物と、日本の伝統文化を、次の世代に伝えていくことが非常に大切だと考えています。こういった知識は、学校、ことに義務教育課程で子どもたちに教えるべきものではないでしょうか。着物の縫い方、着方を学んだり、着る機会を与えることは、個人の能力や情操を高めるだけでなく、地域社会とのかかわりを身に付けることにも役立ちます。

中学校義務教育課程で和装教育を実施してほしい、という趣旨の署名を行ったところ、全国から51万あまりの賛同書名が寄せられました。この要望は、91名の国会議員の方々の紹介を得て、平成10年4月に国会へ請願されました。それから衆議院文教委員会で内容の審議がなされ、全会一致で採択されました。その後、本会に上程され、平成10年6月18日、第142回衆議院本会議において、全会一致で「中学校における和装教育実施に関する請願」が採択されたのです。
このことは、国政の場で、和装教育の重要性と必要性が認められたことを示しています。

国会で採択された「中学校における和装教育実施に関する請願」は、文部省でその措置が検討されました。
文部省中央教育審議会と教育課程審議会から「国際化時代に対応した生きるカを身に付ける教育」が求められる中で、平成10年12月、文部省新学習指導要領中学校技術家庭科の家庭分野項目に、衣服の課題として和装教育を入れることが告示されたのです。この結果、平成14年4月に公表された文部省検定済新教科書(技術家庭)に、和装教育の項目が編纂されました。
和装教育の具体的な内容や実施の方法については、地域や学校、生徒の実態などにより異なるものとされていますが、和装教育の重要性は今後も高まっていくことでしょう。